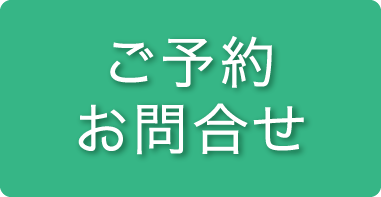中国医学の気、血、津液と栄養
中国医学は、中国において約2000年の歴史を有する医学です。中国医学において、身体を構成し、生命活動を維持するために必要な三要素を「気」、「血(けつ)」、「津液(しんえき)」(日本漢方医学では津液の代わりに水で表します。)といいます。
気、血、津液は、口から入る飲食物が、脾胃(西洋医学における胃腸)によって消化吸収された栄養分「水穀の精微(すいこくのせいび)」から作られます。これら3つの要素は互いに補いあい、制御しあい、依存しあうという関係が成り立ちます。

気は元気の気、病気の気、天気の気などでも表現されますが、エネルギーと言い換えたほうがわかりやすいかもしれません。主に自然界や人間の身体の内外に、目には見えない形で存在しており、生命活動の根幹を担います。身体の中で、細胞を分裂させる、新陳代謝を行う、心臓を動かす、血液を巡らせるなど、身体を動かすものはエネルギーである気の作用と考えます。
そして、血は、水穀の精微から作られます。西洋医学の血液と同じように血管の中を流れる赤色の液体で、臓腑や器官、身体の各細胞に栄養と潤いを与えます。これを滋養といいます。さらに血は精神状態と深い関係があり、血に異常をきたすと驚悸(きょうき)や不眠、多夢、集中力の低下といった症状が起こりやすくなります。
津液は、汗、尿、粘液、リンパ液、細胞外液、関節液など、体内における血以外の液体を指します。飲食物が脾胃に消化吸収され、栄養分である水穀の精微が作られるときに、一部が津液となります。津液は様々な液体の形で存在し、身体に潤いを与え、皮膚や髪など体表を潤しバリア機能を強める、筋肉や関節をしなやかに動かす、また、体温の調整などを行います。
つまり、中国医学における気、血、津液は、飲食物が消化吸収して作られた栄養から作られています。
気、血、津液を動かしてバランスを整える鍼灸治療も、栄養状態の過不足を整える栄養療法も、概念や方法は異なりますが、身体を栄養によって、根本から治していくというベースは同じなのです。